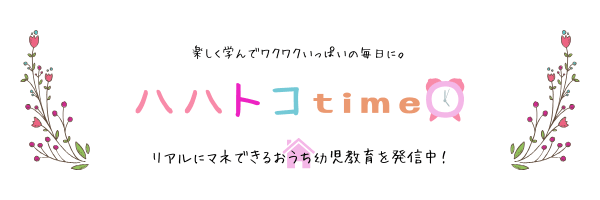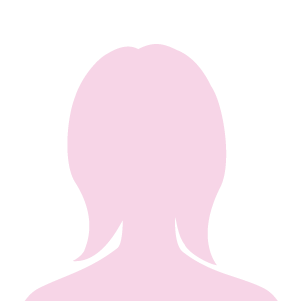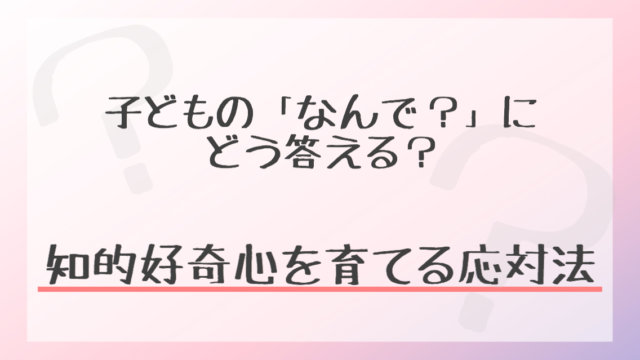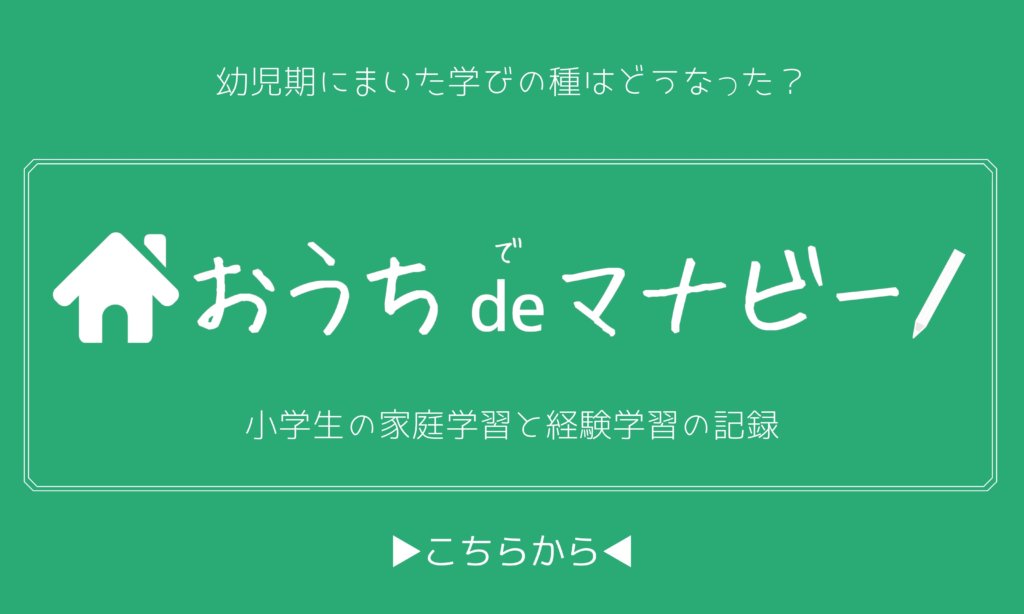4才・5才・6才のお子さんの「なんで?どうして?」の質問に困っていませんか?
3才になる頃から始まる「なぜなぜ期」。
「なぜなぜ期|子供の質問にどう答える?知的好奇心がグッと育つ対応法」の記事でご紹介したように、朝から晩まですることなすことに毎回「なんで?」と言っていた子ども。
でも、5才を迎えるころには具体的な質問になってきていますよね。
そう、端から「なんで?」と聞いていた子が、ある事柄に対して具体的な疑問を持つようになるのです。
例えば、食事をするとき。
3才の頃は、「どうしてご飯を食べなきゃいけないの?」
と聞いていたのに、
5才を迎える頃には、「お腹が空くとなんでお腹がぐ~っと鳴るの?食べたものは体の中でどうなるの?」
こんな感じです。
子どもの質問の内容が、具体的な質問にかわってきたら、こちら(親)も対応法を変えましょう。
具体的な質問は、子どもの好奇心の種。
光を当て、水や肥料を与えることで、芽が出て大きく育っていきます。
具体的な質問をする時期に心がけること
子どもの「なぜ?」に光を当て、好奇心の種を育てるアイテム
ご紹介する応対法・アイテムを使って息子と過ごしたところ、
- 身の回りの小さなことにも疑問を持ち、自分の考えを話せる
- 調べ方を覚え、疑問が疑問を呼び、学びが広がっていく
好奇心・考える力が育っています。
子どもが具体的な質問をする時期がきたら心がけること

なぜなぜ期の中でも、具体的な質問をするようになってきた時期に心がけることは次の3点です。
- 子どもの質問に興味を持つこと
- 子どもへの対応を、できる限り後回しにしない
- 実体験を大切に
一番大切なのは、子どもの質問に興味を持つこと
具体的な疑問は「好奇心の種」とお話ししました。
種を育てていくには、光と水が必要です。
光となるのは、抱いた疑問に対して親が興味を持つこと。
子どもに向き合い、抱いた疑問にスポットを当ててあげることで、子ども自身が「自分をしっかり見てくれている」と、安心して周囲にアンテナを張り活動できます。
水となるのは、具体的な疑問の答えを見つける手段を提供すること。
「子どものなぜ?の答えを見つけるためのアイテム」でご紹介するものを提示することで、知識はもちろん、答えに至るまでのプロセスなどもどんどん吸収していきます。
できるだけ後回しにしない対応法
子どもが疑問を持ったとき、できればその場で答えを一緒に考えられるのが理想です。
でも、
- 手が離せない家事などをしている
- 出先ですぐに調べたりできない
こんな時も多いですよね。
せっかくできた好奇心の種。
「今忙しいから」・「また後で」「おうちに帰ってから」・・・
そうしているうちに、好奇心の種がこぼれ落ちてしまいます。
すぐに調べることができない時は、とりあえず光だけ当てましょう。
- あなたが疑問を持ったことママ(パパ)も知りたい
- 疑問に対する答えの導入部分だけサラッと話す
- フワッとした疑問だったら、整理してみる
口頭だけのやり取りでも、「ママパパがあなたのことをきちんと見ている」と子どもに伝わり、導入部を話したり疑問点の整理をすることで、記憶にも残ります。
お落ち着いて調べられる状況になったら、改めてお子さんと一緒に調べてみましょう。
実際に実験する・見る・聞く体験を大切にする
情報をかみ砕いて説明するのも良いですが、百聞は一見に如かず。
実際に実験する・見る・聞く体験を大切にしましょう。
言葉にできないものってたくさんありますよね。
できるだけ実体験をさせてあげられるのが理想です。
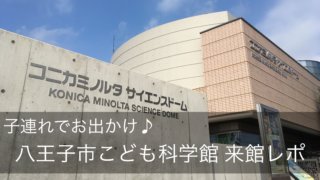
子どものなぜ?の答えを見つけるためのアイテム


子どもの好奇心を育てていくのに必要なアイテムは、次の4つです。
- 図鑑
- 絵本
- 児童書
- 地球儀
アイテム①図鑑|質問期に1番活躍する
子どもの質問期に一番役に立つのが図鑑です。
通常の分類ごとの図鑑には、ダイナミックで鮮やかな写真の他にも、ミニ知識やコラムもたくさん載っており、疑問を深堀していくのにぴったり。
テーマごとに1冊の図鑑にしたものは、調べるだけでなく眺めたり、読み物としても利用できます。
公園で見かけた花や虫などを家に帰って調べる
図鑑を読み物として楽しみ、出かけた時などに、「図鑑でみたね」とリンクさせる
家にいながら、写真やイラストで様々な事物を網羅できる
カタカナが読めないと引けない
索引の使い方を根気よく教える必要あり
図鑑で調べようと思っても、子どもが自分で使えるようになるには時間が必要です。
アイテム②絵本|子どもにも理解しやすい
絵本は、言葉だけでなく絵や図解が豊富。
だから、子どもでもわかりやすく、お子さんが自分の力で答えにたどり着けます。
子どもの「なんで?どうして?」を扱った絵本
「はじめてのなぜなにふしぎえほん」は、日常の中で子どもが出会う疑問が70以上載っています。
身体を扱った絵本
身体を扱った絵本は、自分の体に興味を持っている、うんちやおしっこという言葉が好きな幼児期の子どもたちにおすすめ。
ご紹介したいのは、かこさとしさん著の「たべもののたび」。
口から入った食べ物が、どんな風に体の中を通っていくのかとても分かりやすく描いています。
臓器を、「いぶくろこうえん」「しょうちょうこうえん」「だいちょうどおり」と、幼児がとても親しみやすく表現されているところも面白い。
自分の体の秘密・擬人化された食べ物たちがどうなっていくのか、親子で楽しめる1冊です。
地球を扱った絵本
「ちきゅう」は、地球と宇宙の仕組みを描いている絵本です。
どうして昼間は明るいの?
暑い夏と寒い冬が来るのはなぜ?
そもそも地球って何?
ふと気づくと疑問がどんどん湧いてくる、自分が住んでいる地球について理解できますよ。
わかりやすい言葉とイラストで分かりやすい
子どもの質問に関連した疑問も一気に解決できる
読み物として楽しめる
アイテム③児童書
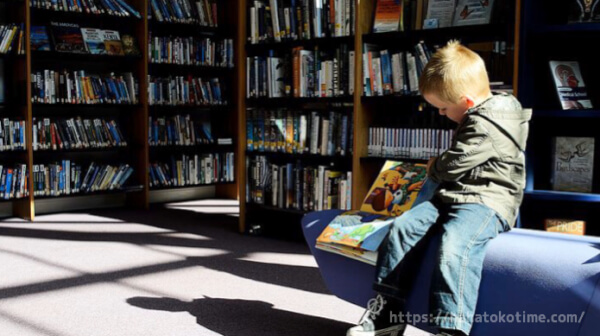
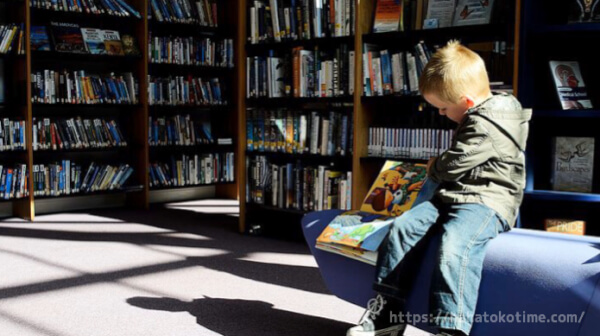
現在は複数の出版社から、子どもが抱く「なぜ?なに?どうして?」にスポットを当てた児童書が出版されています。
1・2年生向けの本には、
- 5才6才のお子さんが疑問に思うような題材
- 身近な題材
が取り上げられているので、おすすめです。
みさき家では、高橋書店の楽し学べるシリーズ「楽しい!かがくのふしぎ なぜ?どうして?1年生」を購入しました。
また、図書館の児童書架を見てみるのも良いです。
小学生が調べ学習にも使うので、写真や図解もあり分かりやすく解説されていますよ。
漢字にルビがなかったり、幼児には言葉が難しい部分もありますが、親子で一緒に調べるにはぴったりです。
息子と図書館で借りてきたのは「清掃工場・最終処分場(調べよう ごみと資源)」という本。
写真がとても豊富で、ごみ収集車が集めたごみがどこへ行ってどうなるのか、息子にとても説明しやすかったです。
「なぜ?どうして?」を扱う児童書は、読み物としても楽しめる。
適度な文量・イラストもあるものは、幼児も親しみやすく絵本から児童書への移行期にもおすすめ
深く物事を知ることができる
本によっては漢字にルビがないもの、言葉が難しいものもあるのでフォローが必要
アイテム④地球儀


身の回りには、さまざまな国のものがたくさんありますよね。
テレビでも毎日、世界各地のことが報道されているし、オリンピックやワールドカップなど、スポーツで国名を聞ことも多いです。
そんな時、
- どこにある国なんだろう
- どういう国なんだろう
そんな疑問は浮かんできませんか?
みさき家では、ワールドカップや世界をテーマにしたバラエティ番組なども、地球儀を抱えて観るのが当たり前になりました。



地球儀があるとすぐに目で見て確認できます。
日本との距離や近隣の国もすぐわかる。
疑問解決がスピーディーなので楽しいし、「自分でできた」を実感できるから、何度もやりたくなります。
子どもが自分で調べやすい
身の回りのすべての物事が地球儀につながる
知る楽しさを実感でき、次にもつながる
カタカナが読めないと見つけられない
地理的な場所しかわからない
国旗図鑑など、国の情報が書かれている本と一緒に使うと、知育効果が倍増します。
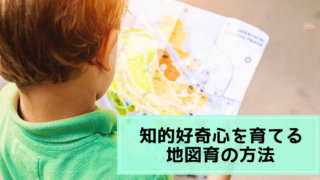
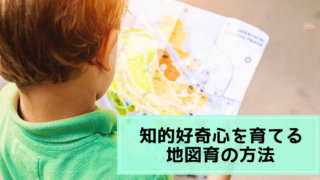
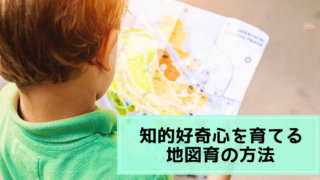
まとめ|身近に図鑑や地球儀を置いて疑問を解決する習慣をつけよう


子どもの知的好奇心がグンと伸びるなぜなぜ期。
4才後半から5才、6才にかけて具体的な疑問を持つようになってきます。
身近な疑問が子どもの口から出てきたら、知る楽しさを教えるチャンス!
パパママが子供の疑問に興味を持つ
疑問を解決するのに必要なアイテムを与える
この2つを実践して好奇心の種を育てていきましょう。
子どもの疑問を解決してくれる4大アイテムは、
- 図鑑
- 絵本
- 児童書
- 地球儀
どのアイテムもメリット・デメリットがあるので、題材とお子さんの理解度に合わせて選んでみましょう。
最初はお子さんと一緒に調べて、考えてを繰り返す。
疑問が浮かぶ→調べる→答えを知る→考察(自分の考えとの違ったこと、一緒だったこと)
このサイクルを何度も繰り替えるうちに、
- お子さんひとりで調べられる
- 論理的な考え方ができる
ようになっていきます。
こうして幼児期に知る楽しさを実感し、疑問解決の手段を身につけることは今後とても役に立つはず。
子どもと一緒に勉強・成長していきましょう。