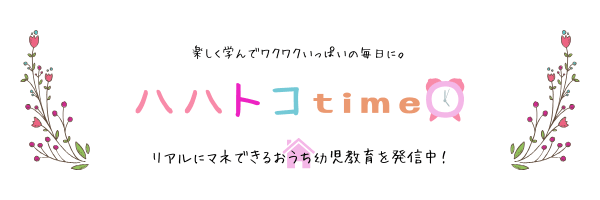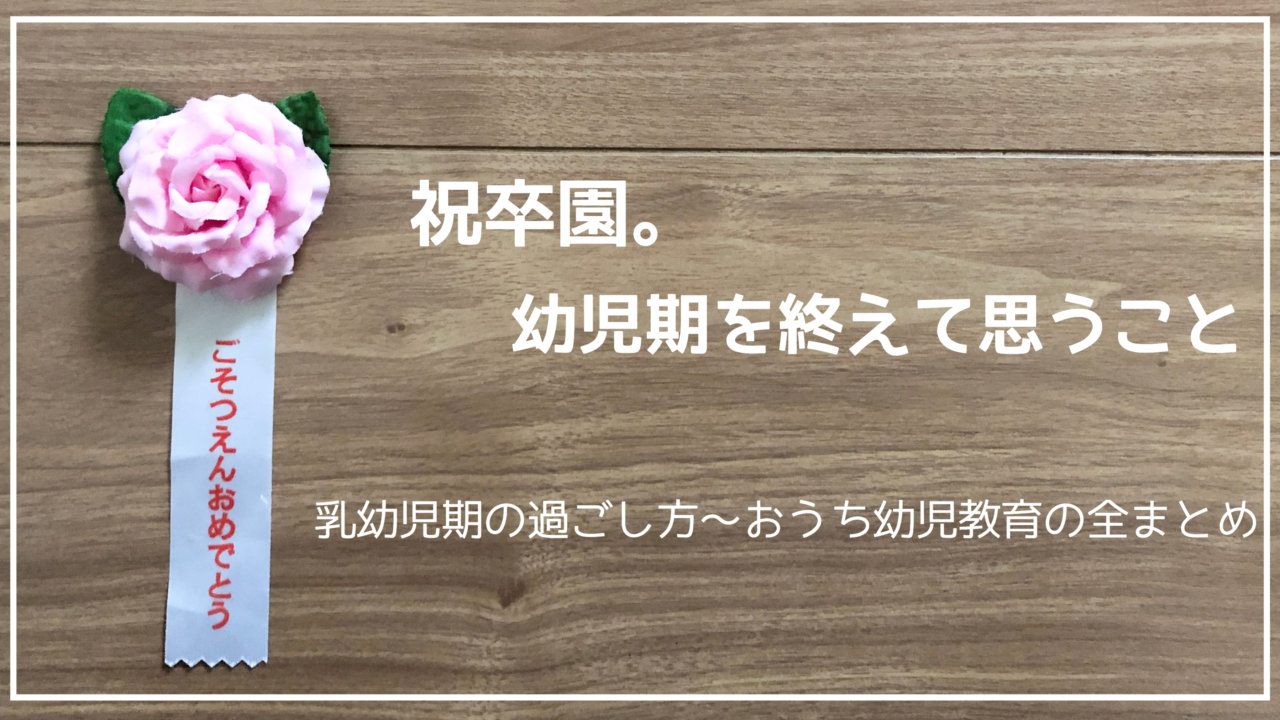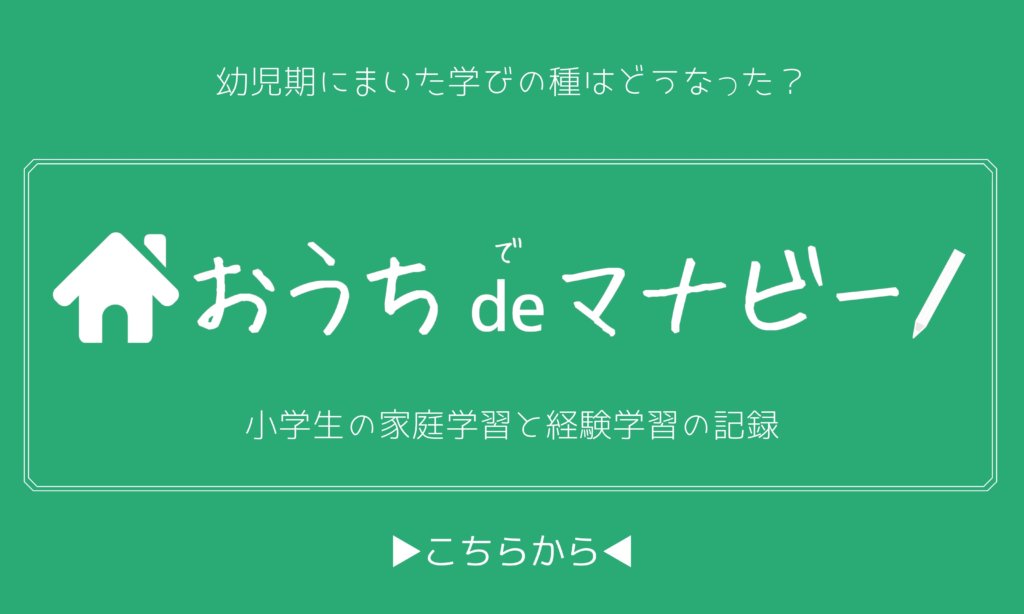2020年3月、息子が幼稚園を卒園しました。
新型コロナウィルスの影響で、3月2日より休園。
- 突然始まった、ちょっと早い春休み
- 厳戒態勢の中での卒園式
卒園の実感がわかないまま、迎えた卒園式。
背筋がピンと伸び、しっかりとした動作で卒園証書を受け取姿に、息子の成長を感じました。
そして、一番感慨深いのが…
ということ。
肌を離さず過ごした乳児期。
肌を離して手は離さない幼児期。
息子との思い出がいっぱいあります。
はからずも、当ブログ「ハハトコtime」100記事目!
今回は、いつもとはちょっと違ったテイストで、
- 息子の成長の様子
- 使用した幼児教育グッズ
- 使用ドリル一覧
- 幼児期終了時できるようになったこと
以上4点についてまとめてみました。
息子0才|肌を離すと泣いちゃう子

0才代の息子との生活を3行にまとめると、
- 慣れない育児に戸惑う
- 毎日生きるのに必死
- 新しい出会い
こんな感じです。
生後0か月~6か月
息子、完母で育てていたのですが…とにかくよく飲む!
そして、背中スイッチならぬ、背中センサー搭載で…
縦抱き大好き!な赤ちゃん。
首が座ったら、おんぶもしくはドーナツ型授乳クッションに寝かせることはできましたが…
とにかく肌が離せない時期でした。
初産だったので、3,4か月検診以降に市の子育て講座(全4回)に参加。
講座終了後も、連絡を取り合って遊びに行ける初のママ友ができました!
生後6か月~
そんな息子もお座りができるようになると、おもちゃで回りをぐるっと囲めば食事の準備ができるように♪
特に、布絵本がお気に入り。
絵本に興味を示すことも多かったので、図書館に通い始めたものこの時期。
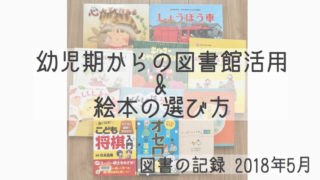
寝返りは8か月とゆっくりだったけど、歩き始めたのは10か月。
ハイハイ期があっという間に過ぎ去りました…
室内で遊べる子育て支援施設や、保育園のホール開放に積極的に参加。
大人と会話することで、私のストレス解消にもなりました♪
成長に合ったおもちゃを使って遊ぶ
子育て支援施設へ通って広いスペースで遊ばせる
他の子との交流することで親子ともに成長
図書館を利用して読み聞かせに力を入れる
息子1才|活動的だけどママのそばは絶対離れない


1才代の息子との生活を3行にまとめると、
- 支援施設・公園大好き
- 知育デビュー
- 第2子(娘)妊娠&自宅安静で実家を巻き込み子育て
こんな感じ。
0歳代に築いた土台をもとに、私が幼児教育の世界に足を踏み入れていった時期です。
幼児教育に興味を持ったきっかけは、「私が幼児教育をはじめたきっかけ」の記事にて詳しく紹介中。
毎日のよう子育て支援施設に通い、会場を渡り歩いて様々なイベントに参加しました。
歩くのが安定してきてからは、公園遊びが中心に。
砂場遊びが大好きで、大きなお山を作ったりプリンカップと石や落ち葉でケーキを延々と作って遊ぶ。
夢中になりながらも、一定時間ごとに私の存在を確認していたし、家でもトイレまでついてきちゃうくらいママと離れられない子でした。
息子1才半の時に娘を授かり、妊娠初期と後期には自宅安静も経験。
夫も仕事が休めなく、息子と2人で実家にお世話になりました。
知育デビューは「シール貼り」
手作りの「ポットン落とし」にハマる
英語CDのかけ流し開始
マル(円)が書けるようになる
図書館で年間100冊以上絵本を借りた
息子2才|体力お化け


2才代の息子との生活を3行にまとめると、
- お兄ちゃんになり娘のお世話を手伝う
- 歩く。とにかく歩く
- 毎日のルーティンが確立
こんな感じ。
「幼児教育の基本って何だろう?体力と集中力が今後の学習の鍵になる!」の記事でご紹介したように、車も子乗せ自転車もなく、あるのはベビーカー1台。
娘が生まれ、息子は歩くしかありません。
あまりイヤイヤがなかった子だったので、そこまで苦労することなく息子が歩ける範囲での生活を楽しむ毎日。
その結果、すごく体力がつきました。
そして、午前中の外遊びだけではお昼寝しなくなったので、鉛筆系の取り組みを始めました。
毎日のスケジュールは下記。
(基本的に平日日中は夫不在。朝~19時まで私一人で子供二人のお世話。
合間に娘のお世話&授乳してました。)
- 8:00までに起床朝ご飯を食べさせ、Eテレを見ている間に洗濯・掃除
- 9:30子育て支援施設or公園or図書館&ショッピング天気が悪い日はおうち遊び
- 12:00昼食食後おもちゃで一人遊びしている間に片付け
- 13:00鉛筆系取り組み・お絵かき
- 13:30お昼寝私も一緒に寝落ち・復活できたら夕飯準備
- 15:30おやつ
- 16:00夕散歩スーパー等で買い物・トラックの給油所でトラック観察(笑)
- 17:15夕飯準備
- 18:00夕食
- 19:00~お風呂・就寝準備・読み聞かせ
- 21:00就寝私・息子・娘3人そろって就寝
びっくりしたのは、おむつ外し。
息子2才4か月で大きい方が突然取れ、小さい方もほとんどトイトレしていないのに、ある日突然「トイレ行く!」と言って成功。
その後1週間でおむつが取れました。
息子2才11か月でした。
2才代で取り入れた幼児教育グッズは、
- おしゃべりことば図鑑
- 児童用図鑑
- 子ども包丁
の、3点です。
おしゃべりことば図鑑は、たまひよの「にほんご えいご おしゃべりことばのずかん」を選びました。
(この商品を選んだ理由・レビューは、後日別記事にまとめます。)
初めての本格的な図鑑は、小学館の図鑑NEO「水の生物」
(図鑑の選び方については、後日別記事にまとめます。)
台所仕事にも興味を持ち始めたので、息子専用の包丁を購入しました。
詳細については、「台所育児とは。オススメの子供用包丁はこれ!」の記事にて紹介しています。
2才代の使用ドリル一覧
- はじめるえんぴつ(旧はじめてのえんぴつ)
- はじめてのめいろ
- がんばりめいろ
- やさしいかず
- ○(まる)つけ博士レベル1
- 七田式 ちえ できるかな 2.3才

- 100均ドリル各種
体力と集中力の向上
鉛筆を使った取り組みに挑戦台所育児を開始。子供用包丁デビュー
図鑑を購入
数の敏感期(1回目)数の感覚を身につけさせる声掛け
息子3才|知的好奇心が爆発


3才の息子との生活を3行で表すと…
- 知的好奇心が止まらない
- 未就園児の親子教室に通い、ちょっと揉まれる
- 私の体力と気力が崖っぷち
息子3才代の時期に入ると、体を動かした上に頭を使わせてもお昼寝しない…
さらに娘も1才になる前にトコトコ歩きを習得。
マイホーム計画も重なって頭も身体も忙しく、今となってはほとんど記憶がありません(笑)
アルバムやアメブロの育児記録を見返すと兄妹一緒に遊ぶことが多かったよう。
毎日のルーティンも上記に示した2才代の頃とほぼ変わりなく過ごしていたはず。
(変わったのは夫が多忙になり、平日はすれ違い生活だったこと。)
息子本人の成長・興味については、
- ひとりでトイレに行けるようになった(3才3か月)
- チャックをしめられるようになった(3才3か月)
- トーマス大ブーム(アニメ・絵本)
- 100まで数えられるようになる(3才11か月)
この時期取り入れた幼児教育グッズは、
- 100玉そろばん
- 各種ドリル
- 色鉛筆
100玉そろばんは、「【100玉そろばんの選び方】着目ポイントとおすすめ5選」の記事で詳しく紹介しています。
お昼寝しなくなった分、取り組みに掛けられる時間が倍増。
100均や無料プリント、くもんの市販ドリルを中心に、娘がお昼寝中に取り組みをしました。
3才代の使用ドリル一覧
- 100均ドリル各種
- できるよABC(旧やさしいABC)
- かず 100までの数と数量のおけいこ
- はじめてのひらがな 上
- 学研の幼児ワーク ちえ
- 天才脳ドリルプチてんびょうしゃ
100玉そろばんで遊ぶ
鉛筆を使った取り組みに挑戦
台所育児を開始。子供用包丁デビュー
図鑑を増やしていく
ひらがなの読み書き
興味に合わせたドリルで机に向かう練習
Sight Word Readers
数の敏感期(2回目)数の感覚を身につけさせる声掛け
息子4才(年少)|初めての社会で戸惑いの1年


4才の息子との生活を3行で表すと…
- 幼稚園入園で初めての社会にふれる
- 興味の幅が一層広がる
- 会話が楽しい
息子が4才になる年、3年保育の幼稚園に入園しました。
人見知り・場所見知りがひどく、私からほとんど離れたことのない息子。
もちろん最初の1週間は大泣き( ;∀;)
具体的なお話は、「幼児教育と知育の違いって?取り組みで大切な3つのポイントと入園時に役立ったこと」の記事で紹介しています。
幼稚園での様子が知りたくて、ちょっと遠いけど徒歩登園を選択。
娘のご飯のタイミングや自転車乗車拒否も多く、年少の4月から雨の日も夏の暑い日も片道18分ほどかけて一緒に歩きました。
園のお話を聞いたり、しりとりしたり。
四季折々の虫や植物を見つけ、道草しながら一緒に歩いた時間が宝物。
そして、補助輪なしで自転車にも乗れるようになりました!(4才9か月)
4才から取り入れた幼児教育グッズは、
- 絵の具
- マジックブロック
- くもんの日本地図パズル
- ボードゲーム
この4点です。
絵の具は、息子が幼稚園で絵の具で描くことを覚えてきて、放課後教室の「絵画教室」に通いたい!と言ったのがきっかけ。
予算の関係で、教室ではなく絵の具を購入して、おうちでやってみることにしました。
マジックブロックは、ドリル系ではなく、手を動かしつつ頭も使う、一人でできる知育玩具が欲しくてたどり着きました。
夏に地図育を始めて地図への興味が深まったため、くもんの日本地図パズルを購入しました。
地図育の詳細は、「知的好奇心を育てる地図育の方法☆本棚に一冊ちずえほんを置こう!」の記事をご覧ください。
また、ボードゲームにも興味を示し始めたので、オセロ、将棋を購入し、どうぶつしょうぎも手作りしました。
4才の間に取り組んだドリル一覧
- 100均ドリル各種
- あそびのおうさまBOOK はって
- ひとりでとっくん365日01基礎1-A、02基礎1-B、03基礎2-A、04基礎2-B
- こぐま会てんずけい1、2、3(途中まで)
- こぐま会じょうけんめいろ
- こぐま会しほうからのかんさつ1
- はじめてなぞぺー
- 迷路なぞぺー
- 幼児のパズル道場 かずと思考力
5才の息子との生活は、4才の頃とほとんど変わらず(笑) なので、成長・興味についてまとめます。 徒歩2分の距離の公園に自転車で行くところから始め、公道を走るルール・マナーを教えつつ徐々に行動範囲を拡大。 また、この頃から先生やお友だちと一緒に遊ぶことが楽しいと感じられるようになりました。 さらに、年中の3学期からは自分からお友達を誘ったり、「いーれーてー!」と自ら遊びの輪に加われるように! 一緒に遊びたいけど、声をかけるのが苦手な息子。 そこをクリアできるように担任の先生との面談でお願いしていました。
息子5才(年中)|1歩踏み出す勇気が持てた
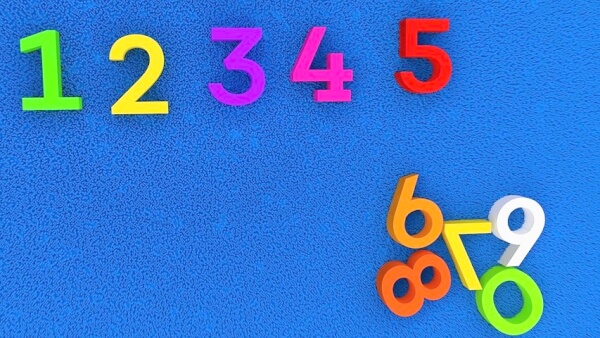
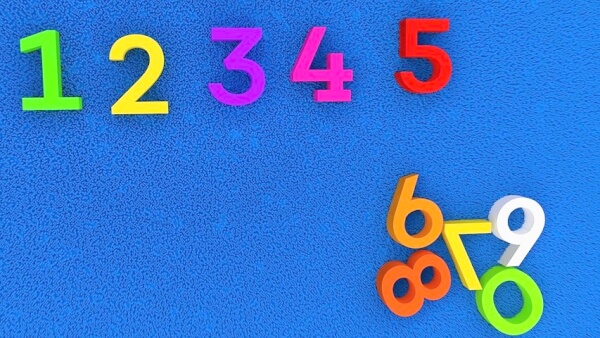
(それまでは、自由遊びの時間にひとりで堰堤を散歩したり、砂をいじっているような子でした(;’∀’))
息子の興味が広がり、できることが格段に増えた年中の春にZ会 幼児コースの受講を開始。



さらに、園生活にも余裕ができてきたので、一番興味関心があったピアノを習い始めました。
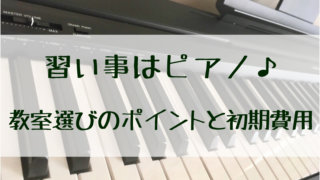
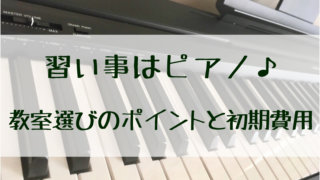
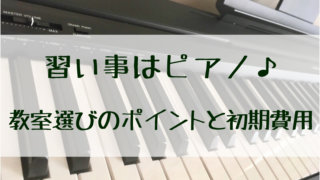
5才から取り入れた幼児教育グッズは、
- クルリグラフ
- ラッシュアワー
- タブレット教材
- 地球儀
この4つ。
クルリグラフは、集中力アップ・色彩感覚を養うのに最適。
詳細は、「『クルリグラフデラックス』で遊んでみた!」の記事で紹介しています。
ラッシュアワーは1人で遊べる脳トレパズル。
子どもから大人まで楽しめます。
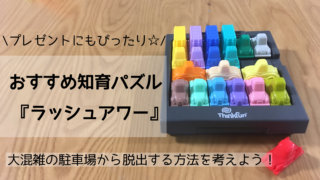
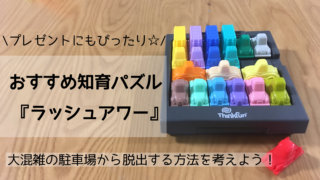
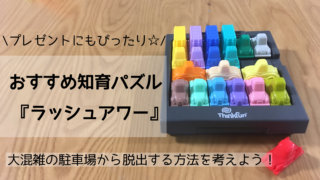
そして、あまり良いイメージのなかったタブレット学習教材。
思いかけず体験できることになったので、お試ししてみたら…



5才の間に新たに取り組んだドリル一覧
- 100均ドリル各種
- 天才脳ドリル 仮説思考 初級
- ひとりでとっくん365日05
- 通信教育各社のサンプルワーク
6才になった息子の成長・変化は、 この4つです。 6才になる頃には、特に仲の良いお友だちができ、 明日は○○君と遊ぶんだ♪ とか、 お友だちにお手紙書くから、ママは見ないで! と、より積極的に友達にかかわれるようになりました。
息子6才(年長)|幼稚園が楽しくてたまらない


以前までは、ちょっとでもうまくできないと途中で投げ出していたのに、失敗してもめげずに挑戦し続けられるようになりました。
地道な努力が必要な「なわとび」や、「お箸を持つ」練習もコツコツと。
なわとびは2重とびまでできるようになったし、食事もお箸のみで食べられるようになりました。
関連記事:子どもにお箸の持ち方を教えるには?必要なアイテム・練習法を大公開!
さらに、大嫌いだったプールも、「できるようになりたい」という思いが強くなり、教室へ通うように。
水が怖くて潜ることもできなかったのに、卒園する時には、顔をつけてけのびができるようになっていました。
6才の間に新たに取り組んだドリル一覧
- ひとりでとっくん365日06~09
- もじパズル
- 通信教育各社のサンプルワーク
- きらめき算数脳 入学準備~小学1年生 ずけい・いち
- きらめき算数脳 入学準備~小学1年生 かず・りょう
ここまでたくさん書いてきましたが、息子の乳幼児期を終えて思うことは、 “元気に、ここまで育ってくれてよかった” これに尽きます。 そして、息子のことをよ~く見て、たっくさん考えてやってきた「おうち幼児教育」は私自身の学びにもなったし、とても楽しかった。 (うまくいかない時やイライラする時。停滞時期もあったけど(;’∀’)) ハハトコtimeでご紹介してきた「おうち幼児教育」に息子と取り組んだ結果、 体力がついた 特に学習面では心配なく小学1年生を迎えられました。 これから学校で勉強として習う時に、 「あっ!これ知ってる!」 とか 「見たこと、聞いたことあるな」 と幼児期の経験がフッとよみがえる。 そんな機会が訪れたら嬉しいなと思います。
乳幼児期を終えて思うこと
知的好奇心が育った
学習習慣がついた
幼児期にまいた種が芽を出し、大きく成長しますように!
勉強も人間関係も、自分のことも大変な時期。
これまでとは違った壁にぶち当たったりすることもあるでしょう。
これからは息子を信じて手を離しつつも、目は離さず。
息子の成長を見守りたいと思います。
小学生の家庭学習については、別サイトにて紹介していきます。
現在、サイト準備中!
開設できしだい、こちらでもアナウンスさせていただきます。
幼児期に必要なのは知識の詰込みではなく、
体験や経験から「考えること」「気づくこと」
それが後々役に立つ!
【あと伸び力を育てるZ会】
\資料請求はこちらから/
![]()
![]()